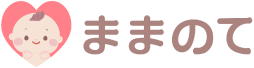【2023】お正月飾りはいつからいつまで?門松・しめ縄・鏡餅!種類や飾り方・処分法をご紹介
著者:ままのて編集部
-
門松、しめ飾り、鏡餅など、お正月飾りにはさまざまな種類があります。新しい気持ちで新年を迎えるにあたり、それぞれにどのような意味が込められているかご存知でしょうか。ここでは、お正月の飾りの紹介や飾るタイミング、処分方法などをご紹介します。お正月飾を上手に飾って、縁起良く新年を迎えましょう。
本ページはプロモーションが含まれています
お正月飾りの種類や意味は?
お正月を祝う理由として、もともとは田の神、豊作の神と呼ばれる歳神(としがみ)様をお迎えするためとされてきました。お正月飾りは歳神様を迎える準備として古くから続いている日本の風習です。
それぞれの飾りが持つ意味を順に見ていきましょう。門松

引用元:https://cdn.mamanoko.jp/attachments/4a12a692723ab6a7105efad0940d79948d5d3489/store/limit/620/620/54319b62bad9f0f3f04b872ac4e199331d97bd69428493b009dcfb9c183f/image.jpg
門松は山から下りてきた歳神(としがみ)様が迷わないように、目印として門に松を飾ったことが起源だと考えられています。門松には、松や竹などさまざまな材料が用いられていますが、それぞれに意味があります。
・松…冬でも緑の葉をつけていることから長生きを表します。
・竹…まっすぐに伸びることから神聖であることや長生きを表します。
・ウラジロ(シダの葉)…歳を重ねるという意味の「しだる」にかかっています。葉の裏が白いことから、潔白を表しています。
・紙垂(しで)…災いが家に入り込むのを防いでくれると考えられています。
京都の旧家や社寺では、根引き松という根が付いた松の若木を半紙でくるみ、水引で結んだ門松が飾られています。お正月を京都で過ごす場合、注意深く見てみると面白いかもしれませんね。